お世話になります。
 の、高橋です。
の、高橋です。
今回は
「業務改善にAIをどう使うか?」
というテーマで、個人的な見解や見聞きした実績を共有します。
結論として、現段階ではほとんどの中小企業において
AIの活用は様子見というスタンスで問題ないかと考えます。
AIをウリにした営業マンが来ても意に介さぬ態度で大丈夫です。
従業員の貴重な時間を使ってAIを試させる必要もありません。
ただ、ごく一部の作業は効率化の役に立つ場合があります。
(例:音声や画像や文書の解析処理など)
そのため従業員に対してAIの使用を禁止する必要もありません。
AIの試用を希望する従業員がいるのなら、
期限・予算・成果を決めて好きにやらせてみてもよいでしょう。
そのうち、AIを使いこなす優秀な外注業者が
海外を中心に隆盛するものと予想します。
日本には言語と文化の壁が一定あり、
海外のIT業者がまだまだ大量流入しにくい現状がありますが
いずれ日本人がAIエキスパートであるインド人を大量に引き連れて
IT業界に押し寄せ、AIの価格破壊を発生させることでしょう。
そのような時代になれば
いよいよ自社でAI技術を磨く必要も薄くなります。
数多あるAI業者に相見積もりを取って選定すれば
御社もAIへの対応が完了する、という算段です。
おそらくAI業者への相見積もり依頼は、
それがたとえ冷やかしであっても
遠慮なく半無制限的に行ってよいものと思います。
AI業者それ自体の業務処理
(問合せ受諾、原価積算、与信判定、見積生成などの営業事務作業)
については、既にAIにより運用されているため
こちらがどれだけ依頼をかけても
AI業者としては僅かなコストで対応できるだろう、
というのが遠慮が要らぬ理由です。
逆接的に表現すると
冷やかしの見積依頼に対し難色を示すAI業者は
自身の内部業務が大して効率化されておらず
自社内でAIがそれほどうまく活用できていない、
ということになり、
その(自社内でも大して役立っていない)劣悪なAIを売ろうとしている
悪質業者である、と判断することができるかと思います。
AIに限らずですが、目新しい技術について
様子見のステージはいくつかあります。
1.大企業のごく一部が導入する
※過去にブームとなったRPAはこのステージで頓挫、衰退しました
2.大企業に普及する
3.大企業が作るソフトウェアにその機能が盛り込まれる
4.無料で使える製品が充実してくる
5.同規模の同業他社でちらほら実例を聞くようになる
6.営業マンからの電話が増える
また、ソフトウェアそれ自体の性質として
「後発のメリット」というものが必ずあります。
焦って飛びつくと稚拙な機能を高値で掴まされる恐れがあります。
上記の5あたりまで様子見し、それから検討されるのが
ソフトを買うことについては手堅い判断になると予想します。
本日もお疲れさまでした。
------------------------------
■直近、前後コラム案内■
<<< ひとつ新しいコラムへ進む Vol.138 - 非効率の許容、不合理の許容、属人化の継続 2023.04.28
>>> ひとつ古いコラムへ進む Vol.136 - 「かかるものはかかるんです」これが正直に言えぬソフトハウスは皆倒産してしまった 2023.02.27
TEL:050-5236-3104
こちらにお電話ください。
担当不在の場合は、後ほど折り返しいたします。
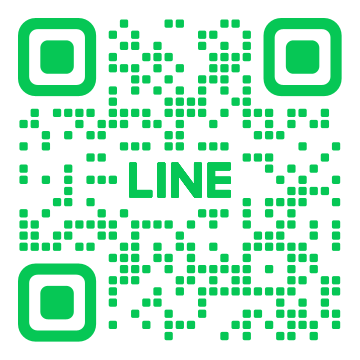
LINE公式アカウントでのご相談対応も承っております。
QRコードをスキャンするとLINEの友だちに追加されます。
QRコードをスキャンするには、LINEアプリのコードリーダーをご利用ください。