お世話になります。
 の、高橋です。
の、高橋です。
インボイス制度の開始まで1年を切りました。
今年の初頭あたりから顧客各社との意見交換を重ね
おおむねですが対応の方針はほぼ一定のものとなりました。
今回は、当制度に対するわたしたちとしての概見を
コラムとして述べます。
ヨソ様はどうしているの?と気になる社長さんは多いでしょう。
以下お伝えする現場の肌感を参考に留めてください。
1.正直なところ、何をするにも骨折り損のくたびれ儲け
当制度は国つまり税収増加のために制定されたルールであり、
企業の重要性の原則とはかけ離れたものです。
真っ当に対応するにしても、しないにしても、
当制度は本業利益に大きく影響しない要素にかかわらず
人件費あるいはシステム費がかさむお話です。
2.面倒でも、制度について自社主導で勉強すべし
当制度に対し、具体的にどう対応するか?については
業界の習慣と取引先の事情と所轄税務署や担当税務官の組み合わせで
各社それぞれ異なるものです。
消費増税や軽減税率の令とは違い、
今回はみんな国税の言うことを素直に聞くとは限りません。
制度の概要は把握していながらも、
各者異なった独自の解釈で運用してゆくことが予見されます。
そのため、面倒でも自社のことは自社で勉強し
当制度にどう適応するか、あるいは適応しないのか
社長さんが自ら判断されるのがいちばん安上りになるといえます。
3.士業の先生方でもアテにならない場合がある
顧客と顧問契約をしている先生方とも
いくつかお話をする機会がありましたが
知識・意識の水準は統一されておらずバラバラです。
先生方と直接付き合いがないので発言できることですが
ご高齢の先生ほど、ズレた解釈をしていると
感じることが多くありました。
特に社内で使っている請求書/納品書発行システムについて
内部仕様を把握していることは稀です。
これは仕方のないことですが、
当制度の対応にはシステムの変更を伴うこともあるため
本件は要留意事項です。
4.まずは簡易的な対応の検討を
現段階では、という前置きが必要ですが
各社長さんの発言として「正直者が馬鹿を見る」という意見が
圧倒的に多数を占めました。
少なくとも、当制度を積極的に肯定する方には会ったことがありません。
・今は外部費用がかかるシステムの改修は行わない
・手書き、ハンコで都度対応する
・本格対応は外部から指摘を受けてから考える
など、可能であればまずは簡易な対応を行い、
世間様の様子を伺うというスタンスで問題ないでしょう。
本日もお疲れさまでした。
------------------------------
■直近、前後コラム案内■
<<< ひとつ新しいコラムへ進む Vol.133 - 業務を改善するためには再現性の概念が必要 2022.11.22
>>> ひとつ古いコラムへ進む Vol.131 - 従業員にシステム会社の相手を任せることの功罪 2022.09.05
TEL:050-5236-3104
こちらにお電話ください。
担当不在の場合は、後ほど折り返しいたします。
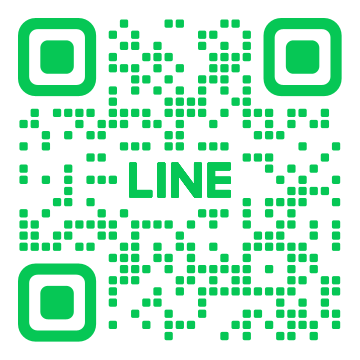
LINE公式アカウントでのご相談対応も承っております。
QRコードをスキャンするとLINEの友だちに追加されます。
QRコードをスキャンするには、LINEアプリのコードリーダーをご利用ください。