お世話になります。
 の、高橋です。
の、高橋です。
クラウドの良し悪しや導入可否を判断検討される前に、
そもそもクラウドは何か?
自社(オンプレミス)のサーバーとどう違うのか?
について概念的なことを知っておくのは、よいことであると思います。
「自社サーバーにシステムを入れることと、クラウドサーバーにシステムを入れること」
の違いは、ひとことで言うと
「発電機を回して電気を使うことと、コンセントに差して電気を使うこと」
のような違いがあります。
詳細を以下に述べます。
①設備の準備規模が違う
発電機方式で電力を得る場合は、自分でその発電機(と燃料)を用意する必要があります。
コンセントから電力を得るのであれば、発電機(発電所)を自分で用意する必要はありません。
自社サーバーでシステムを組む場合は、自社でそのサーバー機を用意する必要があります。
クラウドサーバーでシステムを組むなら、サーバー機(データセンター)を自社で用意する必要はありません。
②設備メンテや維持にかかる責任(つまり労力)の違い
自社の発電機が故障したら、その責任は自社にあります。
コンセントに電力を送る発電所や送電設備の故障は、電力会社にその責任があります。
自社サーバーの破損は自社に責任があります。
クラウドサーバー(データセンター)の破損は、クラウドの提供会社にその責任があります。
③契約(金銭負担タイミング)の違い
発電機を調達する際にはまとまった代金を支払う必要がありますが、毎月の支出はありません。
コンセントから電力を得たければ、発電所を買う必要がない代わりに毎月の基本料金を電力会社に支払う必要があります。
自社サーバーは買うときにまとまった費用が発生します。
クラウドサーバーはデータセンターを買う必要がない代わりに、毎月の利用料を支払う必要があります。
④性能を良くしたいときの違い
発電機の出力を増強するには、発電機を買い足すか買い換えるかの判断が必要です。
コンセントから得る電力を増やすには、毎月の基本料金をUPする必要があります。
自社サーバーの増強は、基本的には買い替えを行うのが現実的でしょう。(買い足しは難しい)
クラウドサーバーの増強は、契約の切り替えを行えばOKです。月額を大きくすれば性能が上がります。
⑤性能を低くしたいときの違い
増強した発電機の性能をもとに戻す場合、発電機の買い足しに払った経費はムダになります。(発電機が余るので)
コンセントから得る最大電力を減らしたければ、契約アンペアを減らせばOKです。毎月の基本料金が下がります。
買い換えた自社サーバーの性能を元に戻すことはできません(技術的には可能でも、あまり意味がない)
クラウドサーバーを小さくしたい場合は、契約の切り替えを行えばOKです。契約性能を小さくすれば利用料は下がります。
⑥好き勝手できるか?の違い(する必要があるかはさておき)
自社で持っている発電機は自社で好きに改造できます。
コンセントは好みに改造できず、ある程度決められた範囲の工事しかできません。
自社サーバーは用途を自由に決められ、どんな極端なセッティングを行うことも可能です。
クラウドサーバーはデータセンター自体が他のユーザとの共用であるため、あまり変なことはできません。
⑦性能固定化・自動進化の違い
発電機は、基本的に買ったときの仕様で使い続ける必要があります。
発電所は、電力会社が安定供給のための性能強化を日々行っています。
自社サーバーは、基本的に買ったときの仕様のまま変わりません。
クラウドサーバーは、提供会社が日々速度・安定性・セキュリティ・自動バックアップ、などの性能を日々向上させています。
⑧付帯サービス(これはクラウドのみ)
クラウドサーバーは各社しのぎを削り、
「専用窓口の設置」「新機能の追加」「連携サービスの新設」など付帯サービスの充実を図っています。
⑩前提要件が違う
発電機はガソリンがあればどこでも使えます。
コンセントは電線が来ていない場所には引けません。
自社サーバーは電源とLANと端末があればどの事務所にも設置できます。
クラウドサーバーはインターネット環境があればどこでも使えますが、回線のない環境では原則使えません。
長々と書きましたが、上記まとめると
「クラウドとオンプレの違いは、発電機とコンセントの違いと似ている」です。
これだけ覚えていれば、よほど凝ったことをしない限り、クラウドの検討や選定はスムーズにできるようになるでしょう。
本日もお疲れさまでした。
------------------------------
■直近、前後コラム案内■
<<< ひとつ新しいコラムへ進む Vol.82 - 海賊版ソフトを使っていませんか? 2018.03.04
>>> ひとつ古いコラムへ進む Vol.80 - 今も昔もシステムはトラブルがあって当たり前 2018.01.10
TEL:050-5236-3104
こちらにお電話ください。
担当不在の場合は、後ほど折り返しいたします。
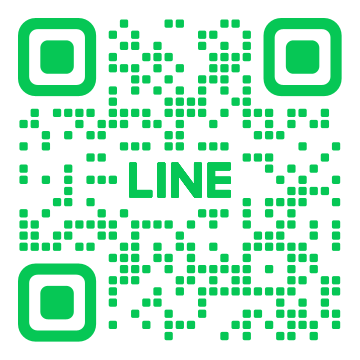
LINE公式アカウントでのご相談対応も承っております。
QRコードをスキャンするとLINEの友だちに追加されます。
QRコードをスキャンするには、LINEアプリのコードリーダーをご利用ください。